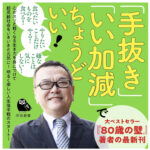夏が過ぎ、涼しくなる季節。
暑さ寒さも 彼岸までという言葉もあるくらいですから、
「お彼岸」という文字をあちらこちで見かけるようになります。
「お彼岸」と聞いてもいまいちわからない・・・。
ですけど、
お店で見かける「お彼岸フェア」など覗いてみると、
そこには「ぼたもち」が並んでいたりします。
なぜ?お彼岸には、「ぼたもち」何でしょう?
そもそもお彼岸ってなんですか?
お彼岸とは、
秋分の日を真ん中に前後3日間をあわせた期間です。
その秋分の日を中日(ちゅうにち)といい、
お墓参りに出かける人が大勢います。
お参りすることで、
亡くなった人をしのぶ日がお彼岸なんです。
「ぼたもち」は、お彼岸にお供えするものとして用いられています。
お彼岸といえば、なぜ?「ぼたもち」?
お供え物を売っている青果店とかで品物を見ると
結構高価な果物だったりしますよね。
昔は甘いものが貴重だったため、「ぼたもち」=ご馳走
ご馳走であるので、
お客さんをお迎えしたり、お祝い事などの時に振る舞ったりしてました。
同様にお供え物としても「ぼたもち」は使われていたんです。
だから、お彼岸のお供えも
「ぼたもち」を備える習慣が残っているというわけなんです。
◆補足
「ぼたもち」に使われている、
おもちは穀物が豊かに実り育つという意味合いがあり、
小豆は「魔除け」とも言われています。
お彼岸には、ぼたもち?おはぎ?どっち?
お彼岸にお供えするお餅なんですけど、
「ぼたもち」なのか?
「おはぎ」なのか?
「ぼたもち」と「おはぎ」は同じなんです。
呼び方が違っていたり、加工方法が少し違うだけで
基本的には同じ物。
春にはボタンが咲きます。
そこから「ぼたもち」(牡丹餅)といわれ、
秋には萩ですから、「おはぎ」(御萩)といいます。
「おはぎ」に「つぶあん」というのは、
あずきの収穫が秋のため、新鮮ですから皮ごと使って作るから。
「ぼたもち」に「こしあん」というのは、
春先になるとあずきの皮は硬くなりますから、
皮をとって「こしあん」にしていたからだそうです。
お彼岸の「ぼたもち」 レシピの紹介
子どもと一緒に作る「ぼたもち」もよいものですよね。
作って楽しいし、食べて美味しいし
お彼岸には、おはぎ、ぼたもちがよいですね。
◆材料
・もち米 3分の2
・普通の米 3分の1
(普通のお米を入れると、冷めてもお餅みたいに硬くなりません)
もち米とお米を合わせると、ちょうど1号になるようにします。
お好みで市販の「粒あん」「こしあん」「きなこ」
◆作り方
・コメを洗って30分くらい水に浸しておく
・通常の水加減で炊飯器にセット
・炊けたら混ぜて、熱いうちに水で濡らしたすりこぎで軽くつぶす
・冷めないうちに分けて、つぶあん等で包みます