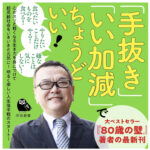さつまいもを料理しようと思い、
包丁で切ったら ところどころ切り口に黒い斑点がありました。
この黒い斑点はなんなのか?
また、食べられるのだろうか?
◆さつまいもの黒い斑点はなに?食べられるの?
さつまいもを切ったときの黒い斑点の正体は「灰汁(アク)」です。
灰汁はほとんどの根菜類に含まれるものです。
そのため、さつまいもの灰汁の場合は、食べてしまっても問題はありません。
灰汁の中には「シュウ酸」や「チアミナーゼ」といった、
体に悪い成分が含まれている場合もあります。
ですが、さつまいもの灰汁には体に悪い成分は含まれていません。
さつまいもの灰汁は、
・ヤラピン
・クロロゲン酸
・タンニン
などが主な成分になっています。
ではひとつひとつ見ていきます。
◆ヤラピンについて
「ヤラピン」は胃の粘膜を保護してくれたり、
腸の働きを良くし便をやわらかくしてくれて便秘の予防・改善になるなど、
腸にやさしい効果があり、身体にはとても良い成分です。
さつまいもを切ったとき、切り口や包丁につく白い液体がこのヤラピンです。
白?なんで黒じゃないのか?
実は「ヤラピン」は空気に触れることで酸化し、黒く変色してしまいます。
その酸化したヤラピンは苦みを出すようになります。
ですので、人によっては黒い部分を食べると、苦みやえぐみを感じるのです。
もちろん食べてしまっても問題はありません。
ですが、味が気になるようでしたらやめておいた方がよいでしょう。
◆クロロゲン酸とタンニン
「クロロゲン酸、タンニン」はポリフェノールの一種になります。
これらは渋みをだす成分です。
ポリフェノール、タンニン特有の抗酸化作用から、
体の酸化の防止や殺菌効果などがあり、体に良い成分です。
食べても問題ないさつまいもの黒い斑点ですが、
気になる場合はどうすればいいのか?
それは灰汁抜きをすればよいのです。
さつまいもの灰汁抜きはどうすればいいのでしょう?
◆さつまいもの灰汁抜き方法
さつまいもを切った後に、すぐに水につけておくと、
灰汁が抜けるため「黒い斑点」がでることも少なくなります。
つまり、灰汁抜きの作業です。
何回か水をかえながら、水が白く濁らなくなる状態までつけこめば、
灰汁抜きは十分です。
◆切り口全体が「黒ずんでいる」ような場合
もし黒い部分が「斑点」ではなく、
切り口全体が「黒ずんでいる」ような場合。
それは「灰汁」が原因ではありません。
その黒ずみは低温障害です。
さつまいもを低温で放置した場合などに生じるものです。
冷蔵庫に入れた場合や、冬に寒い場所に置いていたような場合に起こります。
この場合も食べても問題はありませんが、おいしくない場合が多いです。
その部分は捨ててしまったほうが良いでしょう。