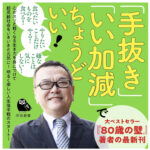なぜ?こどもの日に柏餅やちまきを食べるのでしょう?
その由来とはどんなものなのか?
子供に聞かれてもうまく説明できない
というかしらない
今回は端午の節句の柏餅と「ちまき」についての由来を
簡単にこどもに説明できるようにまとめてみました。
◆こどもの日の柏餅の由来について
こどもの日に、なぜ柏餅が食べられるのか?
そもそもなんで柏餅という名前なのか?
柏餅を巻いている葉っぱ「柏」の木ですけど、この木がもともと縁起物なんです。
神社にお参りする時に「柏手を打つ」なんていいますよね。
その柏手は柏の木から来ています。
では?なんで「柏」の木は縁起が良いものなのか?
秋も深まり葉の色が紅葉から茶色に変わると、
通常その葉は落ちるものなのですが、
柏の茶色い葉は、春の新芽が出るまで落ちることなく残ります。
その様子から、
「子供が生まれるまで親は生きている」
「子孫が途絶えること無く続く」
などの縁起の良い意味があると考えられていました。
「柏の葉」=「子孫繁栄」として、
お餅を柏の葉でまく柏餅を子供の成長を祝う、こどもの日に食べるようになりました。
◆こどもの日のちまきの由来について
柏餅は日本で生まれたものですが「ちまき」は中国から入ってきた文化です。
「端午の節句」とともに
昔中国にいた屈原という人が5月5日川に身を投げてしまいました。
それを悲しんだ人達が供物を投げ入れて弔いました。
しかし、供物は屈原のもとに届く前に龍に盗まれてしまいます。
そこで、もち米を龍の苦手な楝樹(れんじゅ)の葉っぱで包み、
また龍の苦手な五色の糸で縛ってから川にささげると、
無事に屈原のもとへ届くようになりました。
そこから「ちまき」には「難を避ける」という意味があるのだそうです。
このように中国では五月五日の節句には「ちまき」を食べるようになり、
それが日本に端午の節句行事とともに伝わってきたのが由来です。
粽は端午の節句のルーツとなるエピソードで、重要な役目を果たしています。
◆まとめ
鯉のぼりの吹き流しも本来は五色なんですけど、
その色もちまきに関係があります。
ちまきを縛った糸も五色であり、
「難を避ける」という意味を子供が無事に育つようにとのことで、
鯉のぼりの吹流しの色としても使っているんです。
節句の行事は一つ一つが意味のあることなんですね。
今回の柏餅やちまきにもちゃんと意味があり、調べてみると奥が深くて楽しいものです。