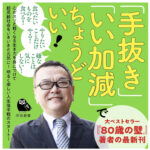おせち料理ですけど、
やっぱり昔からあるということや、おめでたい正月ならではの物ですから、
それぞれの品につきやっぱり意味とかあるんですよね。
毎年気にせずパクパク食べていましたけど、
思い起こせば、おばぁちゃんが説明してくれたような気がします。
そんなことをふと思い出したので、
おせち料理の意味や由来を調べてみました。
おせち料理の歴史 由来について
おせち料理の起源は何時の時代なのか?
個人的には江戸時代かな?と思っていたんですけど、
歴史はもっと古くて、「弥生文化」の時代まで遡るみたいです。
かなり古い歴史ですよね。
その前は縄文時代でまだ米作りが始まっていません。
弥生時代から米作りが始まり
その豊作を願うことから始まったとされています。
季節折々の農作物が収穫できますから、
その季節ごとの節に収穫物を神様に供える
そのことを「節供」というんです。
でね、そのお供え物を料理して食べる「節供料理」、
これがおせち料理の始まりです
おせち料理は神様へのお供え物が由来なので、
やはりひとつひとつの料理にはちゃんと意味があるということなのです。
おせちを入れる重箱の意味
おせちを入れる重箱にも意味があります。
重箱は重ねますよね。
重ねるということばから
「福が重なる」
「良いことが重なる」という意味があります。
たんなるお弁当箱ではなかったんですね。。。
おせち料理の意味
おせち料理ですけど、その品物種類は豊富です。
ですが、
それぞれにやはり意味が込められています。
◆おせち 意味 ア行
「あわび」
アワビは高級食材としても知られていますが、
その身は長く伸びることから
「末永く幸せに」とか「発展」のいみがあります。
「うなぎ」
うなぎのぼり(鰻上り、鰻登り) という
「上昇」「発展」の意味があります。
「えび」
エビに関してはその姿形から縁起物としています。
例えば
「ヒゲが長い」「腰が曲がっている」
そこから「長寿」という意味合いがあります。
◆おせち 意味 カ行
「かまぼこ」
おせちで使われる「紅白蒲鉾」ですが、
まずはその形が初日の出の形に似ていること。
紅白は、縁起物やめでたいものに使用されています。
意味合い的には
赤は「魔除け」
白は「清浄」を意味していると言われています。
「数の子」
数の子はその卵の数の多さから
「子宝」と「子孫繁栄」を願う意味があります。
また、数の子はニシンの卵ですから、
「二親(にしん)から多くの子が出るのでめでたい」とも言われています。
「菊花かぶ」
菊の花は長寿象徴。
時期的に旬であるカブを菊型にして紅白にすることで
「長寿」と「魔除け」「清浄」を意味しています。
「金冠(キンカン)」
キンカンは金の冠と書くことから財宝を意味しています
「黒豆」
「まめ」とは「誠実で真面目」という意味から、
「まめに働く」
勤勉でよく働くという意味が込められています。
「栗きんとん」
栗きんとんのきんとんは「金団」
これは財宝を意味しています。金のお団子でしょうか?
「くるみ」
くるみって割ろうとすると結構固く守られていますよね。
そのことから「家庭円満」家庭を守るという意味で用いられています。
「くわい」
「芽が出る」ということで、出世や成長を意味しています。
また「芽が出る」=芽出たい(めでたい)という意味もあります。
「ごぼう」
おせちにあるのは「たたき牛蒡」が多いです。
牛蒡を叩いて作るわけなんですが、
叩くと開いていきますよね?
ですから「開きごぼう」ともいわれ、開運の意味があります。
また、
「ごぼう」の姿も細く長く地中にしっかりと根を張ります。
そのことから、幸せがしっかり長く続きますようにとの願いです。
「こんにゃく」
おせちで作るのは「手綱こんにゃく」
これは、「手綱を締める(気持ちを引き締める)」とか言いますよね。
そういう意味です。
「昆布」
昆布巻として出てきます。
昆布は「喜ぶ」。。。よろこんぶ。。。ダジャレ?
そんな語呂合わせで使われています。
また当て字で「子生婦」と書き、
女性の子宝を願っての意味もあります。
「こはだ」
コハダは出世魚です。
(出世魚とは稚魚から成魚までの魚の成長ごとに違う呼び名がある魚)
「出世」という縁起の良いことから用いられています。
◆おせち 意味 サ行
「里芋」
これは芋のなりかたに意味します。
親芋があり、その周りに寄り添う感じで小芋がたくさんできます。
ですから「子孫繁栄」の縁起物としておせちに使われます。
「さくらんぼ」
おせちに入ってりるのは「練り切り」といって
和菓子です。
それをさくらんぼの形にしたもの。
「さくらんぼ」
つらなっていますよね。
それを夫婦と見立てて「夫婦円満」の願いを込めています。
「鰆(さわら)」
お魚の鰆(さわら)ですが、これも「コハダ」と同じ出世魚です。
また、
春の魚と書くように旬が春のお魚であるので
春を知らせる縁起ものとして用いられています。
「しいたけ」
おせちに入っている椎茸ですけど、
加工がしてありますよね?
「飾り切り」といって何かを型どっているんです。
椎茸の場合は、
「亀甲しいたけ」といって亀の甲羅を型どっています。
亀は万年といい「長寿」の意味があるわけです。
「酢だこ」
タコをおせちに入れるのは、その色が紅白だからです。
また当て字で「多幸」と書いたりします。
読んで字のごとく幸せが多くありますようにとの願いです。
「するめ」
するめの当て字「寿留女」
寿を留める女ですから、
女性の健康や幸せを願ってのことだと言われています。
◆おせち 意味 タ行
「田作り」
田作りとは、
田んぼや畑に小魚を肥料としてまいたことからその名の由来が来ています。
五穀豊穣を願ったたべものとしての意味があります。
「伊達巻」
大切な文書は巻物だったんです昔は、
ですから、学業や教養といったこと願っています。
「鱈(たら)」
棒だら煮などとしておせちに入れます。
(ちなみに棒ダラは鱈の干物のこと)
意味は語呂合わせで「たらふく食べる」という豊かな生活の願いです。
「たけのこ」
たけのこの成長は早いですよね。
その成長を繁栄として見立てているわけです。
「ちょろぎ」
漢字を使って「長老喜」「千世呂木」と書きます。
長寿を願うという意味。
「筑前煮」
おせちにある「筑前煮」これは別名「七宝煮」といいます。
七宝とは
仏教において、貴重とされる七種の宝のことですから、
七種を使っていることで
筑前煮はそう呼ばれている縁起のよい食べ物なのです。
◆おせち 意味 ナ行
「なます」
人参と大根と調味酢で「紅白なます」を作ります。
紅白の色が縁起が良いとされています。
「錦玉子」
黄身と白身の2色で「二色玉子」が語呂合わせで
「錦玉子」として縁起を担いでいます。
◆おせち 意味 ラ行
「れんこん」
穴があいていることから、将来の見通しがきくようにとの願い。
まとめ
以上がざっと調べたおせち料理の意味となります。
他にも地域によって
違うものがおせちに加えられたりします。
秘密のケンミンショーとかで見たりして知るんですけど、
まだまだ、いろいろありそうですよ。
メジャーな、おせちの意味だけでも知ることで、
おせちの楽しみが増えると良いですね。